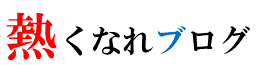こんにちは。甲斐です。
WordPressが普及し、少し勉強すれば誰でもWebサイトを作成する事が可能になりました。
しかし、対外的に信頼感のある、デザイン的にしっかりとしたWebサイトを作りたい場合は、やはりWebサイトの制作会社に依頼するのが一番だと思いますし、実際に「結果が出せる」Webサイトを作成されている会社は多く存在します。
ところで、Webサイトの制作を依頼された場合、当然それは「契約」なので契約書を締結する事が望ましいでしょう。
ただ、一口に契約書と言っても「Webサイト制作を受任する上での契約書の特有のポイント」と言うのがあるんですね。
そこで今回は、Webサイト制作会社の為に、Webサイト制作を受任する上での契約書の特有のポイントをお話したいと思います。
なお、契約書の一般的なポイントは下記のページをご覧下さい。
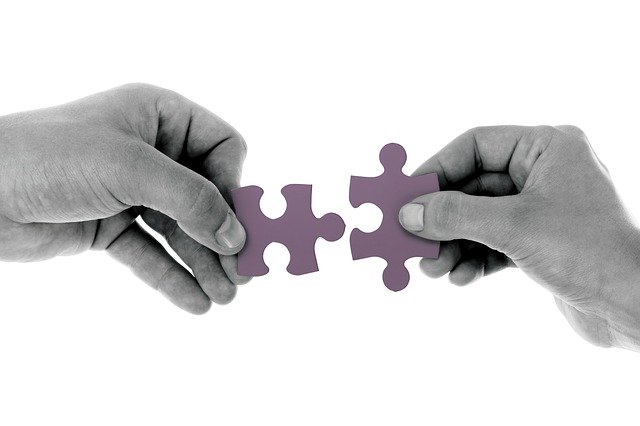
2020.10.08
業務委託契約書を作成する上での基本的な考え方と構成について
こんにちは。甲斐です。Webサイトの作成や何らかのコンサルティング業務を受注した際、「業務委託契約書」を作成する事があると思います。...
1.仕様について
まず最初のポイントは「仕様」に関する事です。
Webサイトを作成する場合、ページをいくつ作るのか?画像をどうするのか?と言った仕様を決める事が多いと思います。
仕様を明確に決めていなければ後からお話する「検収」も出来ませんし、そもそも仕事が完成したと言えず、報酬がもらえない可能性も出てきます。
「●●の機能も当然に実装していると思ったので、報酬はまだ払いません。」
こんな感じですね。
その仕様を契約書の中で明確に決め、お互いの認識をすり合わせる事により、後から「言った言わない」のトラブルを未然に防ぐ事ができるのです。
なお、場合によっては仕様の内容が非常に多くなる事もあると思いますので、
- 「仕様は別紙に定める内容による。」
- 「仕様は当事者の協議で別に定める。」
と言った方法を取っても良いでしょう。
その場合は、別紙に「令和●年●年●月締結の●●契約の仕様は下記のとおりとする。」と言った文言を最初にいれて、具体的な仕様(Webサイトの機能等)を書き込むと良いでしょう。
2.著作権について
続いては著作権についてです。
Webサイトのような「無体物」(財産だけど具体的な形がないもの)については、作成した人が著作権者になります。
つまり、Webサイトを作成した会社が著作権者ですね(クライアントが報酬を支払っただけでは、著作権はクライアントに移転しないのです!)。
ただ、Webサイトを制作した会社はクライアントから依頼を受けてサイトを作成し、その対価を得るわけですから、著作権がそのままWebサイト制作会社にあってはおかしな話になります。
その為、契約の内容として、「制作したWebサイトはクライアントに帰属する」等と言った取り決めをする事が一般的です(著作権は譲渡も可能です)。
ただ無条件に著作権の帰属先を決めてしまいますと、色々と困る事があります。
例えば、クライアントから報酬を支払ってもらえない場合ですね。お金は手に入らないのに成果物であるWebサイトを持っていかれるのはフェアじゃないでしょう。
その為、「Webサイトの制作費をすべて支払った段階ではじめて著作権がクライアントに移転する。」と言った条項にすると言った工夫が必要になってくるでしょう。
3.著作権をクライアントに移転させる場合の注意点
① 翻訳権、二次的著作物利用権の移転
著作権をクライアントに移転させる場合の契約書の条項の注意点として、「著作権法第27条、第28条の権利も移転させる」ことを明記する必要があります。
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
著作権法第27条は「翻訳権」、第28条は「二次的著作物利用権」と呼ばれ、Webサイトのプログラムやコンテンツを修正する権利、修正後のシステムやWebサイトを利用する権利がこれに該当します。
じつは契約書で「Webサイト制作会社からクライアントに著作権が移転する」と記載されていても、上記の著作権法第27条、第28条の権利も移転の対象と含むことが明記されていない限り、移転の対象としなかったものと推定されるのです(著作権法第61条2項)。
(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
上記の推定規定がある為、著作権を譲渡する場合は著作権法第27条、28条の権利も移転することも明記しましょう。
このような感じです(甲がクライアント、乙がWebサイト制作会社)。
第●条
成果物の著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む)は、 甲が乙に対して代金を全額支払ったときに、乙から甲に移転する。
② 著作者人格権について
「著作者人格権」は著作権とは別の権利で、
- 著作物を公表する、しないを決める権利
- 著作者の氏名の表示をする、しないを決める権利
- 著作物を無断で修正されない権利、等
と言った内容の権利です。
そして、この著作者人格権は法律上「移転できない権利」ですので、著作権がクライアントに移転したとしても、著作者人格権はWebサイト制作会社に残る事になります。
つまり、このままではクライアントがWebサイトの修正等が出来なくなる為、契約書の中で著作権が移転されることだけではなく、「Webサイトの制作会社がクライアントに対して著作者人格権を行使しないこと」を明記する必要があります。
具体的には、以下のような内容です(甲がクライアント、乙がWebサイト制作会社)。
乙は本成果物について、甲及び甲が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。
4.検収について
最後は「検収」です。
「検収」は法律用語ではなくその定義は正確に決まっていませんが、通常は
「納品された成果物について、契約の内容に照らし合わせて問題がないかチェックする。」
と言う意味で使われています。
Webサイトの制作で言えば、「事前に決めた仕様に従ってWebサイトが制作されたか?」です。
この検収で問題になるのが、「無制限にクライアントの検収を認めても良いのか?」と言う点です。
細かい部分までクライアントから指摘をされ、検収を何度もやり直されて結局報酬を支払ってもらえない、と言った可能性もありますので、検収に関するルールもしっかりと契約書の中で決めておく必要があります。
そのポイントは以下の3つです。
- 検収の期間を明確に定める。
- 上記の期間内にクライアントから異議が無ければ、検収に合格したとみなす。
- クライアントの曖昧な気分で検収が行われないよう、検収の基準を定める。
最低でのこの3つのルールは契約書に明記するようにしましょう。
5.まとめ
Webサイトの制作はそれなりに時間がかかりますし、報酬も低くはありません。
その為、お互いが気持ち良く仕事をする為、しっかりと契約書を作成するようにしましょう。
契約書についてお困り、お悩み事がございましたら、お気軽にご相談下さい。