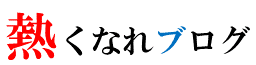こんにちは。甲斐です。
会社は一人で設立する必要はなく、例えば昔からの知り合いの仲間とか、ビジネスコミュニティで知り合った人と一緒に設立する事は可能です。
この場合、いわゆる出資割合(株式保有率)をどうするのか?と言う問題があり、例えば二人で会社を設立して出資比率が同じの場合、会社の経営に関する事について意見の不一致があった場合、会社として意思決定が出来ず、機能不全に陥ってしまいます。
実はこれ以外にも複数の人達で会社を設立する場合、様々な問題が出てくる可能性があるのですが、その問題を解決する為のポイントとなるのが今回ご紹介する「創業者株主間契約書」です。
この創業者株主間契約書は、創業時の株主が複数いる場合、絶対に作成した方が良い契約書です。その理由や契約書の内容を今回、分かりやすくお話したいと思います。
1.創業者株主間契約書とは?作成した方が良い理由は?
創業者株主間契約書とは、創業者間で締結する株式の保有や譲渡などに関するルールを定めた契約書のことです。
最近はスモールビジネスを行うため、一人で起業する(一人株主=社長)のマイクロ法人の設立が増えていますが、その一方で何人かの友人やビジネスパートナーで出資し会社を設立、そのまま全員が取締役になると言うパターンも良くあります。
それぞれのノウハウ・スキルを経営に活用できますので、一人で会社を設立、経営をするよりもスピーディーに規模を拡大する事が可能です。
その一方、先程お話しました同じ出資比率にしてしまった為、会社経営の意思決定について問題が発生したり、結果として創業者の内の一人が経営から手を引く際に、その創業者が保有している株式を巡ってトラブルに発展する事が良くあります。
経営者はその名の通り会社経営に本来注力するべきであり、このような創業者間の株式を巡るトラブルに時間とエネルギーを割くべきではありません。
このようなトラブルを未然に防止し、万が一トラブルになった場合も迅速に対応する事ができるのが「創業者株主間契約書」なのです。
共同経営者が会社経営をやめる場合の持ち株に関する処分等について予めルールを決めておくことにより無用なトラブルを避ける事が出来ますし、何より今後も良好な人間関係を継続させる事できます。
「会社を設立する段階でそんな事を考えるなんて縁起が悪い・・・」と思われるかもしれませんが、人と人が真剣にビジネスに取り組むためには、後々トラブルがあった場合にどうするのか?をちゃんと考える事が必要不可欠なのです。
2.創業者株主間契約書がなければ起こる具体的なトラブル
共同経営者の株式のトラブルで良くあるのが、「経営を辞めたい役員がいるけれど、その株式の買取価格の合意ができない」と言うトラブルです。
出資金は返還する義務はありませんので、共同経営者の一人が経営から離れる(取締役を辞める)ても、株式はそのまま、つまり「株主のまま」です。
と言う事は株主として経営に参画できますので、会社側としては色々と面倒な事になります(株主総会を開催する際に、その辞めた元取締役に通知しなくてはいけませんし)。
その為、会社や他の取締役が辞めた取締役の株式を買い取ると言う方法が良く取られるのですが、その買取価格を巡って合意が成立せず、問題が長期化する事があります。
このような時に創業者株主間契約書で、事前に買取価格や買取方法を定めていれば、株式の譲渡で見解の相違が発生するリスクを下げることができます。
3.創業者株主間契約書の内容
① 誰が株式の買い取るのか?
まず、共同創業者が経営から離脱する際、その人が保有している株式について、他の創業者が買い取る事ができる事を明記しましょう。
具体的な名前を記載するか、それとも「社長」と言った役職者にするのか?社長が経営から離脱する場合はどうするのか?等々、具体的な事を決めて行きます。
② 株式の買取価格はどうするのか?
例えば出資した時と同じ金額で株式を買い取るのか?それとも第三者の鑑定による価格にするのか?と言った具体的な事を決めていきます。
取得時と同じ金額で買い取る場合、難しい計算等は必要ないのでスピーディーに手続きができる反面、会社が成長している場合、出資した時の金額と釣り合わない事があります。
一方、第三者による鑑定は公平ですが、その手続に時間とお金がかかります。
このように価格の決め方は様々あり一長一短ですが、創業者間で話し合いを行い納得がいく内容にする必要があります。
③ その他
具体的な株式の譲渡期間や相続が発生した場合の細かいルールも、事前に決めておいた方が良いでしょう。
4.まとめ
最初は同じ目標に向かって突き進んでいた仲間が、経営に関する考え方の違いで会社を去る事は良くあります。
考え方なのでどちらが良い悪いと言う話ではないのですが、ちゃんと別れの事を事前に考えトラブルを未然に防止する事ができれば、お互いわだかまりがなく、今後の人間関係にも重大な影響を及ぼす事が少なくなります。
相手の事を考えれば、ちゃんと別れる時の事も考えるのも重要でしょう。
なお、当事務所では会社設立と同時に創業者株主間契約書のご相談も行っておりますので、分からない事などありましたら、お気軽にご相談下さい。

2020.04.30
お問い合わせ
起業やビジネスに関するご質問、ご相談は下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください(ご相談はzoomで全国対応可能です)。...