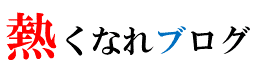こんにちは。甲斐です。
株式会社を設立する際、ほとんどのケースで株式に「譲渡制限」をつけます。
スモールビジネスやひとり会社の社長の場合、ほぼ100%でしょう。
ただこの「譲渡制限株式」、定款や登記事項証明書でその存在を確認する事ができますが、実際に何なのか?と言う点について、会社設立時はあまり意識していないと思います。
ただし、今後幅広く株主を募集したい場合や、数人の仲間と会社を設立した場合、この「譲渡制限株式」は重要になってきます。
特に譲渡制限株式を誰かに譲渡したい場合ですね。
そこで今回は、会社設立時にはあまり意識されない、譲渡制限株式の事をお話します。
1.譲渡制限株式とは?
株式は誰にでも自由に譲渡することができるのが原則です(「株式譲渡自由の原則」と呼ばれています。会社法第127条)。
(株式の譲渡)
第127条 株主は、その有する株式を譲渡することができる。
だからこそ、株式の売買を行い儲けようとしている人達がいるのです。
ただ、スモールビジネスや規模の小さい家族経営の会社の場合、株式が自由に譲渡されると、全く見ず知らずの第三者が株主になるリスクがあり、会社の経営に口を出してしまうこともあるでしょう。
そこで、(株式の譲渡を全面的に禁止は出来ませんが)、株式会社の承認を得ることで譲渡を認める制度があります。
その承認が必要な株式が「譲渡制限株式」と呼ばれるものです(会社法2条)。
なお、会社法上、公開会社と公開会社ではない会社(非公開会社)があり、譲渡制限株式の発行の仕方によってどちらになるかが変わってきます。
(定義)
第2条
5 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
ちょっと文章が分かりづらいですが、株式全部について譲渡制限を設けている会社が「公開会社でない株式会社(非公開会社)」です。
つまり、会社設立の段階で全ての株式に譲渡制限を付けた場合、その会社は「非公開会社」となります。(なので、会社設立のほとんどのケースは非公開会社です。)
2.譲渡制限株式の譲渡を拒否したい場合
先ほどお話した通り、会社の立場で考えると、会社にとって好ましくない第三者に株式を譲渡されることは避けたいでしょう。
例えば数人の仲間と株式会社を設立したけれど、次第に仲が悪くなりその内の一人が会社から抜けたいと思い、誰かに株式を譲渡しようと考えた時です。
もし、株式を引き受ける人(譲受人)が会社にとって好ましくない場合、会社は株式の譲渡を拒否することができます。
なお、譲渡を承認、もしくは拒否する会社の機関は定款に定めている機関が行います。
例えば「株主総会の承認を要する」となっている場合、株主総会で譲渡の可否を判断します。
では、会社が株式の譲渡について承認をしなかった場合どうなるのか?
この場合、通常、会社は請求者から譲渡請求の際に、不承認の場合には「会社または指定買取人に株式を買い取ること」の請求を受けます。
つまり、会社は会社が買い取るのか、または指定買取人を指定するのかを決定しなければなりません。
① 会社が株式を買い取る場合
会社が株式を買い取る場合、株主総会の特別決議が必要になります。
株主総会で株式を買い取る事が決まった場合、
- 1株当たりの純資産額に譲渡する株式数をかけた金額を本店所在地の供託所に供託。
- 請求者に対して譲渡の不承認を通知した日から40日以内に供託証明書を同封して、会社が買い取る事を通知します。
なお、会社が買い取る場合は、自己株式を取得することになりますので、無制限に行えるものではなく、一定の財源規制があります。
② 会社が指定した第三者(指定買取人)に株式を買い取ってもらう場合
会社が指定した第三者(指定買取人)に株式を買い取ってもらう場合は、
- 取締役会設置会社の場合は取締役会の決議
- 取締役会非設置会社の場合は株主総会において特別決議が必要になってきます。
指定買取人が決まったら、指定買取人は
- 1株当たりの純資産額に、譲渡する株式数をかけた金額を本店所在地の供託所に供託。
- 請求者に対して譲渡不承認を通知した日から10日以内に供託証明書を同封して、指定買取人が買い取る事を通知します。
株式の売買価格は、当事者間の合意した金額によって決められます。供託したお金は、売買価格に充当されることになり、売買代金の支払時に株式の移転の効力が生じます。
3.まとめ
譲渡制限株式の譲渡を拒否する場合のポイントの一つは「スケジュール感」です。
会社法所定のスケジュールを従って手続きを行わなければ「譲渡を承認したもの」とみなされます。
また、今回あまり触れませんでしたが、価格の決め方も様々ありますので、譲渡制限株式の譲渡についてご不明な場合は専門家へのご相談をお勧めします。