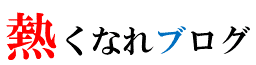こんにちは。甲斐です。
以前、マーケティングに関する法律で「景品表示法(景表法)」のお話をしたのですが、今回はその続きとなる内容です。

2021.01.08
マーケティングで押さえるべき法律「景品表示法」とは?
こんにちは。甲斐です。マーケテイング(広告)の分野を学んでいますと、ユーザーの心を動かす「コピーライティング」の分野も自然に勉強する事に...
この中で景表法では「BtoBは適用外」と言うお話をしましたが、実はマーケティングの分野においてBtoBで適用される法律があります。
それが今回のテーマである「不正競争防止法」で、
- 他の事業者の有名ブランドの表示を無断で使用したり、商品の原産地を偽ったりする等、
- 不正な手段による競争を防止し、
- 事業者間の公正な競争を維持する事で
- 経済の健全な発展を図る事
を目的としています。
なお、他の事業者による不正競争行為が行われ、それによって利益を侵害された事業者は、不正競争防止法に基づく差止請求や損害賠償請求を行う事が出来ます。
1.不正競争防止法の概要
不正競争防止法では不正競争行為として22種類の行為が定められていますが、その内、広告やマーケティングに密接に関係してくるのは以下の6種類です。
- 周知表示混同惹起行為
- 著名表示冒用行為
- 商品形態模倣行為
- ドメイン名に関する不正行為
- 誤認惹起行為
- 信用棄損行為
それぞれ、具体的に見て行きましょう。
2.周知表示混同惹起行為
周知表示混同惹起(じゃっき)行為とは、他社の商品等表示として需要者に広く認識されているものと、同一もしくは類似の商品等表示を使用して、他社の商品または営業と混同を生じさせる行為の事です。
簡単に言えば、
- 事前の承諾や取引関係もないのに、人気のある他社の商品表示を広告中に使用すること。
- 人気のある他社の商品デザインやパッケージを真似たものを用いること。
このような行為が周知表示混同惹起行為に該当する可能性があります。
3.著名表示冒用行為
著名表示冒用行為とは、自社の商品等表示として、他社の著名な商品等表示と同一もしくは類似の商品等表示を使用する事、またはその商品等表示を使用した商品を譲渡する等の行為の事です。
周知表示混同惹起行為との違いは「混同」が要件とされていない事、「周知」では足りず「著名」である事が挙げられます。
簡単に言えば、世間一般に広く知れ渡っている他社の商品等と同一・類似のものを自社の商品などと表示して広告に使用する行為です。
ブランドが世間一般に広まると、それだけで価値を生む事になりますが、他社がそのブランドについて「自社のもの」として使用した事により、ブランドイメージの低下を防ぐ事を目的としています。
例えば高級料理店で有名な「A」と言う名前のお店が、全く関係がない格安料理店が同様の「A」と言う名前を使う事より、「A]と言うブランドイメージが低下する可能性があります。
このように
- 有名ブランドのロゴや形を真似たものを販売したり、広告に使用すること
- 有名ブランド名を店名や商品名にして広告に使用すること
このような行為が著名表示冒用行為に該当する可能性があります。
4.商品形態模倣行為
商品形態模倣行為とは、他社の商品の形態を模倣した商品について譲渡等を行う行為です。
「商品の形態」とは、商品の形状や模様、色彩等、外観上認識する事が出来るものを指します。
「模倣」とは、他人の商品の形態に依拠した(依拠性)、これと実質的に同一の形態の商品を作り出す事(実質的同一性)を言います。
いわゆる「デッドコピー商品」の事であり、これは分かりやすいと思います。
5.ドメイン名に関する不正行為
ドメイン名に関する不正行為とは
- 不正の利益を得る目的で、または他人に損害を加える目的で
- 他人の特定商品等表示と
(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品または役務を表示するもの) - 同一もしくは類似の
- ドメイン名を使用する権利を取得し、もしくは保有し、またはそのドメイン名を使用する行為
の事であり、こららの行為を禁止しています。
有名なのが「sonybank.co.jo」のドメインを取得した被告に対して、ソニーが原告として提訴し、勝訴した事件です。
6.誤認惹起行為
誤認惹起(じゃっき)行為とは
- 商品や役務、その広告、取引に用いる書類、通信に
- 商品や役務の原産地、品質、内容、製造方法、用途または数量について
- 誤認させるような表示をする等の行為
の事です。
景表法の不当表示規制に非常に良く似た内容となっています。
有名なケースとして、競合他社のキシリトールガムと比べて約5倍の再石灰化効果を実現したと言う比較広告が、比較広告の根拠となる実験の合理性が認められず、誤認惹起行為にあたると判断された裁判例があります。
7.信用棄損行為
信用棄損行為とは、競合他社の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したり、または世間に広める行為です。
実際に他社の信用を低下させる必要はなく、低下させる恐れがあればこの信用棄損行為に該当します。
有名なケースとして、LPガスの販売業者が同業他社(A)の顧客に対し、
- 「Aはもう潰れた。」
- 「Aはもう営業していない。」
- 「Aは身売りしたので、もうすぐなくなる。」
等と言って勧誘を行い、行為の差止請求及び損害賠償が認められた裁判例があります。
8.まとめ
結局のところBtoBでもBtoCでも注意すべき本質は全く同じであり、苦労して作り上げた競合他社のブランドにタダ乗りするのは、とても公正な競争とは言えないと言う事です。
そのような独りよがりの姿勢は、クライアントがエンドユーザーであろうとも一般企業であろうとも、簡単に見透かされます。
マーケテイングは「誠実性」が求められる事を十分に意識しましょう。