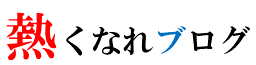こんにちは。甲斐です。
ビジネスに関する法改正は起業家であれば必ずチェックすべき項目の一つです。
今回、特定商取引法(特商法)が改正され、2022年6月に施行されるのですが、今回の改正については主にECサイトの運営者が非常に関係がある改正となっています。
この改正に対応しなければ行政処分等の対象にもなりますので、しっかりと対応するようにしましょう。
1.特定商取引法(特商法)とは?
特定商取引に関する法律(特定商取引法・特商法)は特定の商取引、主に訪問販売や通信販売と言った、消費者トラブルが起きやすい取引を対象として、事業者が守るべきルールを定めた法律です。
(目的)
第一条 この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
【特商法の規制の対象となる取引】
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス)
・特定継続的役務提供(エステ、外国語教室等)
・業務提供誘引販売取引(副業・内職商法)
・訪問購入
これらの取引類型は先程お伝えした通り非常に消費者トラブルが起きやすく、度々改正が行われてきたのですが、今回はECサイト等の通信販売について、消費者保護の為の改正がされました。
「初回無料」「お試し」と書かれていたのに実際には定期購入が条件となっていたり、「いつでも解約可能」と書かれてあったにも関わらず、解約には細かい条件があったり、消費者を騙すような行為が社会問題になり、その問題に対応するための改正となっています。
2.特商法改正でEC事業者に求められること
ECサイト等、インターネットを利用して商品を販売するときの注文確定直前の最終確認画面で、下記6つの条項を表示することが必要になってきます。
① 分量
② 販売価格・対価
③ 支払時期及び支払方法
④ 引渡時期・提供時期
⑤ 申込みの期間がある場合はその旨・その内容
⑥ 申込みの撤回・解除に関する事項
① 分量
商品の数量やサービスの提供回数等がこの「分量」に該当します。定期購入契約の場合は、各回の分量の表示が必要になってきます。
なお、製品やサービスを一定期間利用することができる「サブスクリプション」の場合は、サービスの提供期間と期間内に利用可能な回数があればその内容を表示します。
無期限や自動更新である場合は、その旨を表示します。
② 販売価格・対価
それぞれの商品に対する販売価格に加え、送料等を含めた支払総額も表示します。定期購入契約の場合であれば、各回の販売価格と支払総額の表示が必要です。
サブスクリプションで一定の無料期間から有料に自動で以降するタイプの契約は、その移行時期と支払う金額の表記が必要です。
③ 支払時期及び支払方法
支払時期はいつなのか?支払い方法は銀行振込、クレジットカード決済、代金引換等を表示します。
また、定期購入やサブスクリプションの場合、各回の代金の支払時期を表示します。
④ 引渡時期・提供時期
商品の発送日や発送見込み日、配送日時を指定している場合にはその日時を表示します。
定期購入契約の場合、各回の商品の発送時期を表示します。
⑤ 申し込みの期間がある場合はその旨・その内容
商品の販売に関して申込期間を設定する場合、申込期間がある事とその具体的な期間を表記します。「具体的」なので、良くあるパターンの「今だけ」のような曖昧な表現はNGです。
なお、「タイムセール」と表記しているのも関わらず、その期間が過ぎても同じ価格で販売するのもNGです。
⑥ 申し込みの撤回・解除に関する事項
返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示します。
定期購入契約で解約の申出に期限がある場合、その期限を表示します。
【注意】
申し込みの撤回や解除をする方法が消費者の権利を不当に制限するものである場合、消費者契約法等により無効になる場合があります。
3.特商法に違反したら?
契約した消費者が、違反する表示によって誤認(誤って)契約した場合「取消権」を行使する事ができるようになりました。
具体的には下記のような場合、消費者は契約を取り消せます。
- 不実の表示・・・その表示が事実であると消費者が誤認した場合
- 表示をしない・・・表示されていない事項が存在しないと消費者が誤認した場合
- 申込みに関して誤認させるような表示
- 表示事項について誤認させるような表示
なお、表示に違反があったり、不実の告知があった場合、上記の取消権だけではなく、行政処分や罰則の対象となります。
さらに、これらの違反行為は適格消費者団体による差止請求の対象にもなります。
4.まとめ
今回の法改正は一部の企業の「誤ったマーケティング」の結果によるものです。
この法改正の背景から、「マーケティングとはそもそも何なのか?どうあるべきなのか?」を真剣に考え、顧客のためのマーケティングを考えるきっかけにするのも良いかも知れません。